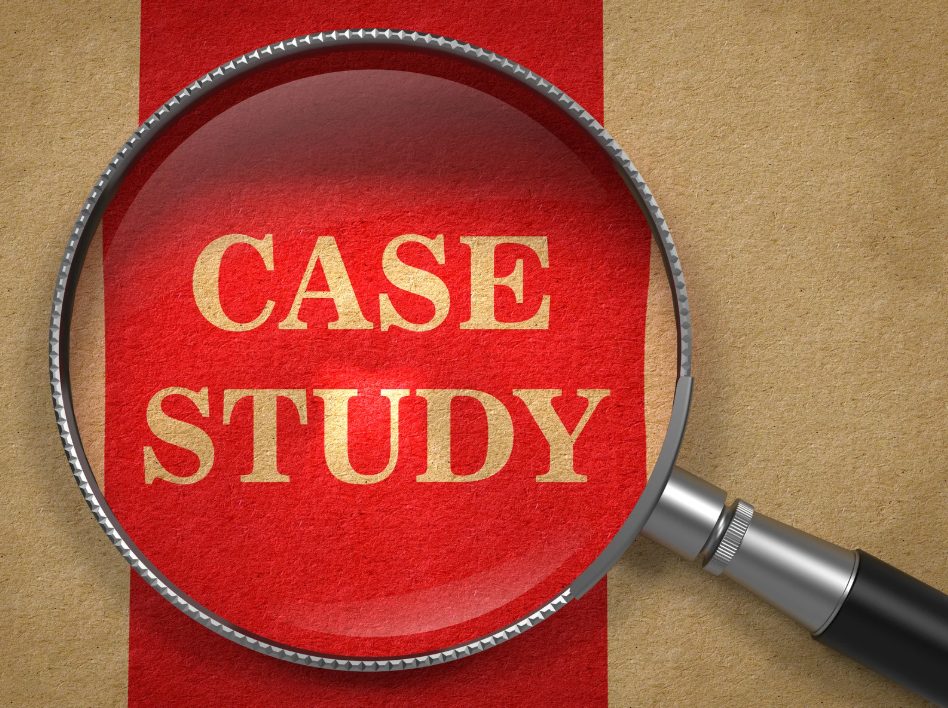餞別のお返しは必要?マナーと相場・おすすめギフトを徹底解説
餞別とは?お返しが必要か迷ったときに知っておきたい基本知識
餞別(せんべつ)とは、これから環境が変わる人に対して贈られる金品や品物のことを指します。たとえば、退職・転勤・異動・留学・結婚など、何らかの理由でその場を離れる人に「これまでありがとう」「新天地でもがんばって」という気持ちを込めて贈られるのが一般的です。
餞別を贈る側は、同僚や上司、取引先、親しい友人などさまざまですが、多くの場合は職場の人間関係において行われる風習です。個人で渡すこともあれば、職場の仲間や部署で連名という形をとることもあります。
このように餞別とは、単なる贈り物ではなく、感謝と激励の気持ちを形にして届ける日本独自の文化だと言えるでしょう。
餞別に対するお返しの必要性と「しなくてもよい」理由とは
「餞別をもらったけど、お返しって必要?」と迷う方は多いです。結論から言えば、餞別に対しては必ずしもお返しをする必要はありません。これは、日本の慣習において、餞別=送別の意味合いが強く、見返りを期待しない贈り物とされているからです。
特に退職や転勤などで職場を離れる際、「これまでありがとう」「頑張ってね」という餞の気持ちが込められているため、形式的なお返しを求めるものではありません。むしろ、すぐに品物で返してしまうと、かえって相手に気を遣わせてしまう場合もあります。
そのため多くの場合は、お礼状やメッセージカードなどで感謝を伝えるだけで十分とされています。ただし、関係性が深かった相手や高額な餞別を受け取った場合などは、後日改めてお返しを検討するのも一つの配慮です。
餞別にお返しをすべきケースとしなくてもよいケースの違い
餞別をいただいたあと、お返しをするべきかどうかは悩ましいポイントです。必ずしも全ての餞別にお返しが必要というわけではなく、その判断には状況や相手との関係性が深く関わってきます。一般的には「退職・異動・栄転」などシーンによって対応が変わることを理解しておくと、失礼のない対応ができるでしょう。
たとえば、退職の際にもらう餞別は、ねぎらいや門出を祝う気持ちとして贈られるため、基本的にはお返し不要とされています。ですが、個人的な想いを込めて贈ってくれた方や、特に親しい相手には、お礼状や品物を通じて感謝を伝えるのが丁寧です。
逆に、異動や栄転などで社内に在籍し続ける場合、関係性が継続することから、お返しをするのが一般的です。お返しの有無は一律に決まるものではなく、「気持ちを伝える手段のひとつ」として柔軟に考えることが大切です。
退職・異動・栄転で異なるお返しの判断基準
餞別のお返しは、その贈り物を受け取ったシーンによって対応が大きく異なります。退職、異動、栄転といった場面ごとに、慣習や相手への配慮の仕方が違うため、それぞれの基準を理解しておくと安心です。
退職の場合、一般的に「これまでの労をねぎらう意味」で餞別が贈られます。この場合はお返しをしないのが基本マナーですが、感謝の気持ちを表すためにお礼状を出す方も多く見られます。特に目上の方やお世話になった上司には、簡単な品物を添えるとより丁寧です。
異動の場合は、同じ会社に在籍しながら部署を移ることがほとんどです。これからも関係が続くことから、お返しは必須に近いとされます。異動前に在籍していた部署全体へのお礼として、お菓子などを差し入れるのが一般的です。
栄転は昇進と同様に慶事であるため、周囲が祝意を示す一方で、本人からの返礼も求められる傾向にあります。この場合、お返しには熨斗(のし)を付けた正式なギフトが選ばれることが多く、特に目上の方には丁寧な挨拶状を添えると印象がよくなります。
お返しが望ましいとされる具体的なシーンとは
餞別に対してお返しが必要になるかどうかは、形式的なルールだけでなく、相手との関係性や職場の文化、贈り物の内容によって判断することが重要です。特に「お返しがあると好印象につながるシーン」は多く存在します。
まず、個人として高額な餞別を受け取った場合は、金額の多寡にかかわらず、お返しをすることで相手に対する配慮が伝わります。気を遣わせない程度の金額で、消えものや日用品などを選ぶと負担が少なくスマートです。
また、職場の有志やチームから連名でもらった場合も、お返しの品を共有できる形で用意すると喜ばれます。個包装のお菓子やドリンク類などはシェアしやすく、実用的です。さらに、異動・転勤などで職場を離れる際に職場の慣習として「お返し文化」がある場合、それに従うのが無難です。
このように、「絶対に必要」というわけではないものの、お返しを通じて良好な人間関係を保つことができるため、迷ったときは「感謝をカタチにする」気持ちを大切にして選択するのが理想です。
餞別のお返しにおける金額相場と失礼のない金額感

餞別をいただいた際に悩みがちなポイントのひとつが「どれくらいの金額のお返しが適切なのか」という問題です。お礼の気持ちを込めて何か贈りたいと思っても、あまりに高額な品を選ぶと相手に気を遣わせてしまう可能性がありますし、逆に安すぎると失礼にあたるのではないかと不安になることもあるでしょう。
この章では、餞別のお返しにふさわしい金額の相場や、避けるべき金額設定について詳しく解説します。
お返しはもらった金額の何割が目安?一般的な相場を解説
餞別に対するお返しの金額は、「いただいた金額の1/3〜1/2程度」が目安とされています。
例えば、3,000円の餞別を受け取った場合は、1,000円〜1,500円程度の品を選ぶのが一般的です。
この範囲であれば、感謝の気持ちを伝えつつ相手に負担をかけずに済むため、無難かつ誠実な対応と言えるでしょう。
また、高額な餞別(1万円以上)をいただいた場合でも、必ずしも同額の半分を返す必要はありません。
特に目上の方や上司などからのお心遣いに対しては、「お礼状+3,000〜5,000円程度の品」で充分です。むしろ、返礼の金額が高すぎると恐縮させてしまうこともあるため、あくまで“気持ち”を伝えることを重視しましょう。
以下に、一般的な相場を早見表としてまとめました。
| いただいた金額 | お返しの目安金額 |
| 3,000円 | 1,000〜1,500円 |
| 5,000円 | 1,500〜2,500円 |
| 10,000円 | 3,000〜5,000円 |
| 30,000円以上 | 5,000円程度+丁寧なお礼状 |
相手との関係性や職場の慣習にもよりますが、この表を参考にすれば大きな失礼になることはないでしょう。
高額なお返しや過度な贈り物はなぜマナー違反になるのか
お返しの目的は、あくまで感謝の気持ちを形にして伝えることにあります。
しかし、過度に高価な品物を選んでしまうと、かえって相手に「気を遣わせてしまった」と思わせる原因になります。とくに上司や年配の方に対しては「見返りを求めている」と受け取られる可能性もあり、注意が必要です。
また、餞別とは本来、門出を祝う気持ちを込めて贈られる好意です。その気持ちに対して「金額的に釣り合う返礼品で返そう」とする行為は、形式的すぎて心が伝わりにくくなります。適度な品と丁寧なお礼状やメッセージを添えることで、より誠意あるお返しとなるのです。
さらに、高額な贈り物は周囲の人との間に差を生んでしまうこともあります。例えば、連名でいただいた餞別に対し、個人の名で高級品を返すと、他の方々が気を悪くするかもしれません。「贈る側の立場」になって考えることが、適切なお返しの第一歩と言えるでしょう。
餞別のお返しを贈るタイミングとマナーを徹底解説

餞別をいただいたあと、「お返しはいつ渡せばいいの?」と迷う方は少なくありません。タイミングを誤ると、せっかくの感謝の気持ちが伝わりにくくなるため、贈る時期や状況に応じたマナーをしっかり押さえておくことが大切です。退職・異動・転勤などのシーン別に最適な時期を見極めることで、好印象なお返しが可能になります。
また、直接手渡しする場合と、郵送や宅配を利用する場合では配慮すべきポイントが異なります。以下で具体的に解説していきます。
退職後や異動後いつまでに贈ればいい?ベストな時期とは
お返しのタイミングで最も重要なのは、「相手の印象に残るうちに感謝を伝えること」です。基本的には、退職・異動後1週間~2週間以内に贈るのが適切とされています。あまりに遅くなると、「忘れていたのかな?」と思われる可能性もあるため注意が必要です。
ただし、退職後すぐは引っ越しや事務手続きで忙しいこともあるため、落ち着いてから1カ月以内を目安に贈るのが無理のないスケジュールといえるでしょう。異動の場合も新しい職場に慣れるまで少し時間がかかるため、同様に目安は「異動後1~2週間」以内と覚えておくと安心です。
また、送別会などで餞別をいただいた場合には、その場で簡単なお礼を述べ、後日あらためてお返しの品と一緒に丁寧なお礼状を添えるのが理想的です。
送別会や最終出社日に手渡す場合の注意点
送別会や最終出社日にお返しを手渡すのは、直接感謝の言葉を伝えることができる貴重なタイミングです。対面で渡すことで、表情や声色からも感謝の気持ちがより伝わりやすくなります。ただし、その際にはいくつかの注意点があります。
まず、手渡し用の袋や包装に気を配ることが基本マナーです。ビジネスシーンにふさわしい落ち着いた色味や、持ち帰りやすいサイズ感を選びましょう。また、連名で餞別をいただいた場合には、人数分の個包装や小分け対応がされた品を選ぶと配慮が感じられます。
さらに、渡すタイミングも重要です。朝の忙しい時間や退勤直前は避け、落ち着いた時間帯や送別会の締めくくりなどを選ぶとスムーズに渡せます。可能であれば、ひとりひとりに対して短くても丁寧な言葉を添えると、より印象に残るお返しになります。
のしの書き方とマナー——表書きや水引の選び方の基本

餞別のお返しをする際には、贈る品物そのものだけでなく、のし紙や水引の使い方にも気を配ることが大切です。形式的なものに思われがちですが、のしには「相手を思いやる気持ち」を形にして伝える役割があります。特にビジネスシーンや目上の方へのお返しでは、のし紙の有無や表書きの内容で印象が大きく左右されることもあるため、正しいマナーを知っておくと安心です。
水引の選び方としては、「紅白蝶結び」が基本です。蝶結びは「何度あっても良い慶事」に使われるため、餞別のお返しに最適とされています。一方、結び切りは「一度きりが望ましいお祝い事」(結婚・快気祝いなど)に使用されるため、お返しにはふさわしくありません。
表書きの文言は「御礼」「感謝」「お礼」などが用いられますが、状況や関係性に応じて適切な言葉を選びましょう。見た目だけでなく、表書きに込められた意味まで理解したうえで選ぶことが、より丁寧な対応につながります。
「御礼」と「感謝」の違いは?表書きにふさわしい言葉とは
表書きでよく使われる「御礼」と「感謝」は、どちらも気持ちを伝えるための言葉ですが、その用途やニュアンスには微妙な違いがあります。餞別のお返しでは一般的に「御礼」が最も広く使われており、あらゆる立場や関係性に対応できるオールマイティな表現といえるでしょう。
「感謝」は、よりカジュアルで親しみのある言葉です。たとえば、同僚や親しい友人に贈る場合には「感謝」の方が柔らかく温かい印象を与えることもあります。一方で、上司や目上の方には「御礼」を選ぶのが無難です。マナーに厳しい方に対しては「感謝」が軽く感じられる可能性もあるため、注意が必要です。
つまり、表書きの言葉は単に見栄えの問題ではなく、相手との関係性や場面に応じて最適な表現を選ぶ配慮が求められるのです。悩んだときは「御礼」にしておくのがもっとも確実な選択と言えるでしょう。
個人宛・連名宛それぞれののしの名入れルール
のし紙の名入れには、個人宛てか連名宛てかで異なるマナーが存在します。まず、個人に対してお返しを贈る場合は、のしの下段中央に自分のフルネームを書くのが基本です。特にビジネスシーンでは姓だけでなく、名まで明記することで、丁寧で誠実な印象を与えることができます。
一方、職場の有志など複数人から連名で餞別をいただいた場合には、のしの名入れもそれに合わせた形式が必要です。この場合は、のし下段に「〇〇部一同」「有志一同」などと記載するのが一般的です。複数人の名前をすべて書くのは避け、まとめた表現で感謝の意を込めるのがマナーとなっています。
また、最近ではカジュアルなギフト用ののしやシール型の簡易のしなども増えてきましたが、名入れに関しては省略せず記載する方が誠意が伝わりやすいため、可能な限り正式な形で対応することをおすすめします。
餞別のお返しでよく選ばれる人気ギフトの特徴と選び方

餞別のお返しには、「失礼がないこと」と「感謝の気持ちがしっかり伝わること」が重要です。そのため、多くの人が選ぶギフトには共通する特徴があります。
例えば、受け取った相手が気を遣わずに受け取れるものや、実用性が高く誰にでも喜ばれやすいものが好まれる傾向にあります。特に最近では、スイーツや食品、タオルや文房具などの「消えもの」や「消耗品」が高い人気を誇っています。
また、贈る相手が「上司」か「同僚」か、「個人」か「グループ」かによっても選ぶべき品は異なります。贈る相手の人数や立場を意識して選定することで、より印象に残る丁寧なお返しとなります。
以下で、具体的なジャンルごとに選び方のポイントを詳しく解説していきます。
お返しに最適な「消えもの」とは?お菓子や食品の魅力
餞別のお返しとしてまず検討されるのが、スイーツや食品といった「消えもの」です。「消えもの」とは使ったり食べたりすれば形が残らないギフトのことを指し、相手の負担になりにくいため非常に好まれます。
中でも焼き菓子・煎餅・紅茶やコーヒーのギフトは、幅広い年代の方に対応できる万能アイテムです。特に個包装されたものは、衛生面でも安心でき、複数人で分けやすいという利点があります。
相手の家族構成や勤務先の人数を考慮して、日持ちするかどうか、好みが分かれにくい味かどうかも確認すると、失敗のリスクを減らせます。なお、ブランド力のある商品を選ぶことで安心感や特別感も高まり、受け取った側の満足度もアップします。
消耗品・オフィス用品・お米ギフトの上手な選び方
お菓子以外でおすすめされるのが、実用性の高い消耗品やオフィス用品、そしてお米のギフトです。これらは性別や年齢を問わず、幅広い層に受け入れられるのが魅力で、特に目上の方へのお返しにも適しています。
オフィス用品なら、名入れボールペンやデスクオーガナイザーなど、ビジネスシーンで活躍するアイテムが喜ばれます。また、お米ギフトは「日本人なら誰もが使うもの」であり、産地や品種にこだわった銘柄米の食べ比べセットなどは特別感があります。
最近では、パッケージに「ありがとう」や「お世話になりました」といったメッセージを印字できるサービスもあり、感謝の気持ちが伝わりやすい点もポイントです。季節や地域の特産品を取り入れた品を選べば、よりオリジナリティを出すことも可能です。
職場全体向けか個人向けかで変わるギフトの選定ポイント
餞別をくれた相手が「職場の有志」なのか「個別の上司や同僚」なのかによって、選ぶべきギフトのスタイルも変わってきます。職場全体から連名で餞別をもらった場合には、皆で分けられるお菓子やドリンクセットなどが適しています。このようなシーンでは、小分けで個包装された品や数の多いセットを選ぶことで、平等に配りやすくなります。
一方、個人からもらった餞別へのお返しは、相手の趣味や生活スタイルに合わせて選ぶことが大切です。例えば、家庭を持っている相手には食品や家族で楽しめるギフト、一人暮らしの方には少量で高品質なグルメ品や雑貨などが好まれます。
どちらの場合も、贈る側の気持ちが伝わるよう、メッセージカードを添えるなどの心配りも忘れないようにしましょう。
相手に喜ばれるためのお返しの渡し方と心配りのコツ

餞別をいただいたあと、お返しの品をどのように渡すかは、相手の印象に大きく影響します。どれだけ良い品を選んだとしても、渡し方に配慮がなければ感謝の気持ちは伝わりにくいものです。
反対に、ちょっとした工夫や心遣いを添えることで、お返しの価値が何倍にも感じられることがあります。状況に応じたスマートな渡し方を心がけることが、円滑な人間関係の維持にもつながります。
この章では、直接手渡しする場合と郵送する場合の違いや、お礼状・メッセージカードの添え方など、細かなポイントを丁寧に解説します。
直接手渡す?郵送する?状況に応じたスマートな対応術
お返しを渡す際は、相手との距離感やタイミングによって「直接渡す」か「郵送する」かを判断する必要があります。
もっとも丁寧なのは、感謝の言葉を添えて手渡しする方法です。特に、退職や異動の前に時間がある場合は、相手の勤務時間内に直接伺い、対面で渡すのが理想的とされています。
ただし、距離やスケジュールの都合で難しい場合は、郵送という選択も失礼にはあたりません。
郵送する場合は、以下のポイントに注意しましょう。
- 配送日時の指定ができる場合は、相手の在宅が予想される時間帯を選ぶ。
- 送り状に「お世話になりました」など簡単な一文を添えると丁寧。
- 品物とは別に、お礼状やメッセージカードを同封する。
また、相手が複数人いる場合(職場の有志など)には、共有しやすいように職場宛に郵送する方法もあります。
いずれにせよ、贈るタイミングや受け取りやすさに配慮することが、相手の満足度を高める秘訣です。
感謝が伝わるお礼状・メッセージカードの書き方と文例
餞別へのお返しに添えるお礼状やメッセージカードは、気持ちを形にして伝える大切なツールです。書き方ひとつで印象が大きく変わるため、内容や文体には十分な配慮が必要です。形式的な文面よりも、感謝の気持ちや近況報告を交えた手書きのメッセージが好印象を与えます。
以下に、ビジネス寄り・カジュアル寄りの文例をそれぞれご紹介します。
| 対象 | 文例 |
|---|---|
| 上司・目上の方 | このたびはご丁寧なお餞別をいただき、誠にありがとうございました。 長年にわたりご指導いただきましたこと、心より感謝申し上げます。 新天地でもいただいたご厚情を胸に、精一杯努めてまいります。 |
| 同僚・親しい方 | 素敵な餞別をありがとう。 寂しい気持ちはあるけれど、新しい職場でもがんばるね。 また近いうちに会えるのを楽しみにしています! |
お礼状に使う便箋は、白地で無地のものが一般的です。
丁寧な字で、1文1文に気持ちを込めて書くことが、相手に好印象を与えるポイントです。メッセージカードを添える場合は、相手との関係性に合ったカジュアルさでまとめると自然な印象になります。
形式ばかりを気にしすぎず、自分らしい言葉で「ありがとう」を届けることが最も大切です。
避けたほうがいい餞別のお返しの例とその理由
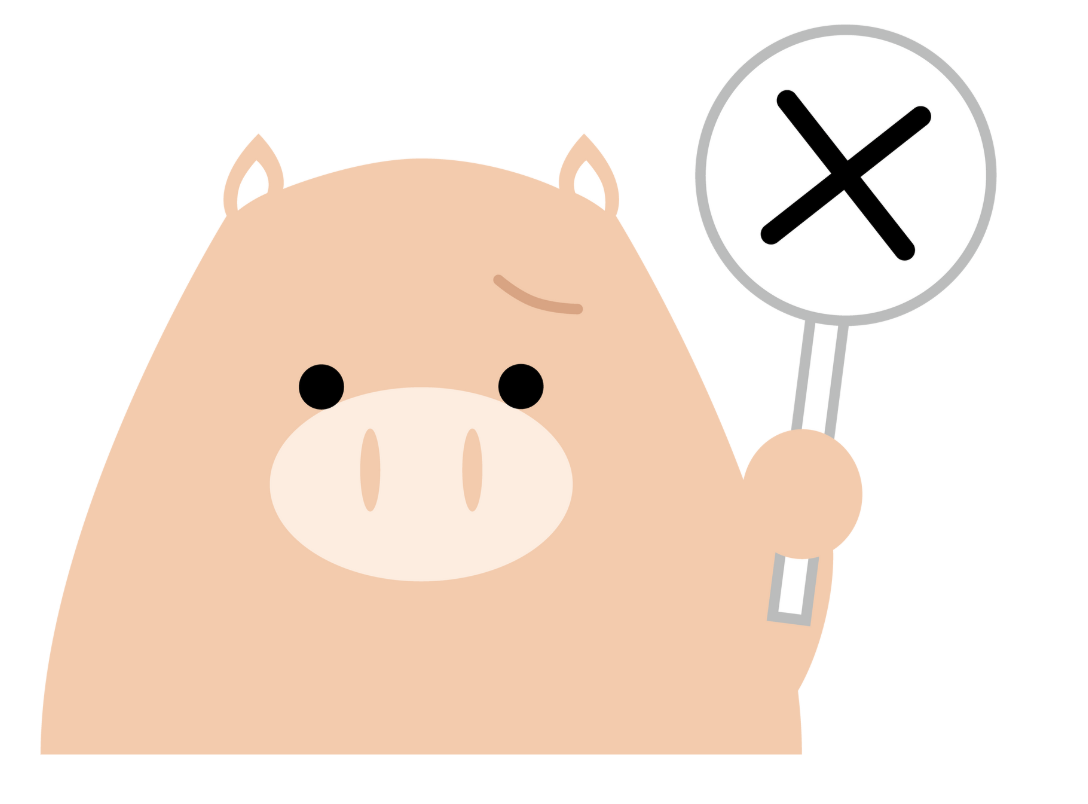
餞別のお返しを選ぶ際には、相手に失礼がないよう慎重に判断する必要があります。
特に「避けたほうがいい」とされる品物には共通する理由があり、選び方を誤ると感謝の気持ちがうまく伝わらないばかりか、かえって気まずい思いをさせてしまうこともあります。
贈る側の誠意が裏目に出てしまわぬよう、贈答のマナーに反するアイテムや不適切な価格帯のギフトには注意しましょう。
マナー違反とされるNGアイテムや高額すぎる贈り物とは
餞別のお返しで避けたほうがよいとされるアイテムには、儀式的な意味を含むものや、公私の線引きが曖昧になりやすい高価な贈り物が挙げられます。
以下のような品物は、お返しとして選ばないほうが無難です。
- 縁起物(昆布・鰹節・酒類):お祝いには適していても、お返しには重々しく感じられることがあり、意図を誤解される可能性があります。
- 現金・商品券・高額ギフト:金額が高すぎると、かえって相手に気を遣わせてしまいます。目安は「いただいた金額の1/3〜1/2程度」です。
- 賞味期限が極端に短い食品:忙しい相手にとっては、早く消費しなければならないプレッシャーになってしまうことがあります。
- 個人の嗜好に強く左右される香水や化粧品:好みが合わないと使ってもらえない可能性が高く、実用性にも欠けます。
また、贈り物の内容に加えて重要なのが相手との関係性と場面にふさわしい距離感です。たとえば、あまり親しくない相手に高額な品を贈ると、ビジネス上の関係を越えた印象を与えかねません。
お返しの目的は「感謝の気持ちを丁寧に伝えること」にあるため、品物のインパクトよりも、誠実で心のこもった内容かどうかを重視して選ぶことが大切です。
餞別におすすめのギフトをご紹介
転勤や引っ越し、色々な新しいスタートついでに、感謝や祝福の気持ちを込めた餞別を贈ることは、日本の美しい伝統の一つです。 ギフトを選ぶには、その人への想いや、共に過ごした時間への感謝が反映されるべきです。 今回は、そんな大切な瞬間にふさわしい、心から喜ばれるおすすめのギフト10選をご紹介します。記憶に残るようなプレゼントとなることでしょう。
「ありがとう」煎餅(10~40枚化粧箱)

「ありがとう」煎餅は、表面に大きく「ありがとう」と書かれているのが特徴です。このお煎餅は国産のうるち米を使用し、しょうゆ味で提供されています。感謝のメッセージが一目で伝わります。
餞別におすすめの理由
このお煎餅は、言葉で感謝の気持ちを代わりに伝えるアイテムとして最適です。 シンプルながら心に響く「ありがとう」のメッセージは、どんなシーンにも合うため、転勤や引っ越しなどの餞別にぴったりです。
【14本入り】シガール

ヨックモックの「シガール」は、バターを豊富に使った洋菓子で、サクサクとした軽い口当たりと繊細な口どけが特徴です。紙箱入りで、贈り物にも適しています。
餞別におすすめの理由
「シガール」は、その洗練された味と形状で、特別な贈り物の時に最適です。 長年愛されているこの商品は、転勤や引っ越しなどの節目において、相手に洗練された味覚と心のこもった感謝を伝えるための餞別としてぴったりです。
銀座フルーツクーヘン16個

銀座千疋屋の「銀座フルーツクーヘン」は、厳選された果汁を練り込んだ生地を一層丁寧に焼き上げた洋菓子です。イチゴ&ミルク、レモン&はちみつ、メロン&ミルク、バナナ&チョコの4種がごはんます。
餞別におすすめの理由
このフルーツクーヘンは、多様なフレーバーが贈り物に新鮮さと選択肢を提供します。 銀座千疋屋の名前が示す高品質と洗練された味わいは、転勤や引っ越しなどの大切な節目での贈り物に最適です。
千なり・焼菓子詰合A

小豆粒あん・抹茶あん・林檎あんの3種の餡を、ふわふわのカステラ風生地で包んだ「千なり」と、人気の焼菓子「旅まくら」「志なの路」「よも山」を詰め合わせた上品な和菓子セットです。季節を問わず喜ばれる通年ギフトであり、多様な味わいを楽しめる構成が魅力。老若男女問わず贈りやすいギフトとして重宝されています。
餞別におすすめの理由
異動や退職などのお礼にふさわしい、感謝の気持ちをやさしく伝えられる詰合せです。個包装でシェアしやすく、職場へのお返しにも最適。日持ちも約10日と扱いやすく、相手の負担にならない点も贈り物として好印象です。
フィナンシェ 2個入

アンリ・シャルパンティエ自慢の「フィナンシェ」は、発酵バターと挽きたてアーモンドパウダーを使った芳醇な味わいが特徴です。オンライン限定の2個入りパッケージは手のひらサイズで上品に仕上げられており、配りやすく高級感のある贈り物として人気です。日持ちやデザイン性も優れているため、気軽に贈れる本格スイーツです。
餞別におすすめの理由
フィナンシェ2個入は、小ぶりでありながら本格的な味わいを楽しめるため、餞別のお返しにぴったりです。配りやすい専用パッケージときちんと感のある見た目は、多くの方に好印象を与えます。手軽さと上質さを兼ね備えており、職場や親しい方への感謝を伝える贈り物として最適です。
京あられ9種

京あられ9種は、最高級のもち米を使用し、伝統的な杵つき方法で作られたあられです。山椒、七味サラダ、黒胡椒など、9つの異なるフレーバーが楽しめる詰めパックで、日本の味をじっくり味わうことができます。
餞別におすすめの理由
この多様なフレーバーのセットは、どんな味覚を持つ方にも喜ばれるため、理想的です。 上品で洗練された味わいは、新しいスタートを切る方への感謝や祝福の気持ちを表現するのに最適です。
ファヤージュ 16個入

「ファヤージュ」は、スライスナッツを敷き詰め、パリッと香ばしく焼き上げた後、選んだチョコレートでサンドしたクッキーです。フランス語で「木の葉」を意味し、その名の通り葉のように繊細です。
餞別におすすめの理由
繊細な食感と豊かな味わいの「ファヤージュ」は、心を込めた餞別にぴったりです。クッキー、ナッツ、チョコレートの絶妙なバランスは、新しい門出を迎える人に完成された喜びを提供します。
プチハートサラダあられ(洋風袋)

ハート型にくり抜かれたかわいらしいあられで、味は「プレーン」「エビ」「青のり」の3種類を楽しめます。職人が手作業で仕上げたあられは、軽やかな食感と香ばしい風味が魅力です。見た目も華やかで、小粒ながら食べやすさと彩りの両方を兼ね備えています。
餞別におすすめの理由
一袋ごとにかわいらしいデザインで、シール対応もできるため感謝の気持ちをメッセージと共に伝えられるのが魅力です。小分けサイズで配りやすく退職時や異動時のプチギフトに最適。気軽に受け取ってもらえ、餞別のお返しとして好印象を与えられます。
オリジナルメッセージ入りどら焼き 小どら (30個入り)

この小どら焼きは、直径約6.5cmのミニサイズで、厳選された国産素材を使用して職人が手作りしています。特別な機会に合わせて15文字のメッセージをカスタマイズして入れることができます。
餞別におすすめの理由
このどら焼きは、オリジナルメッセージを入れることができるため、転勤や退職の際に個々の感謝や祝福の言葉を直接伝えるのに最適です。
リーフパイ 26枚入り

リーフパイ26は、国内産のバターと小麦粉を使用し、256層に折り畳んで職人が手作業で仕上げた洋菓子です。サクサクとした食感とホワイトザラメ糖の食感が魅力の一品です。
餞別におすすめの理由
このリーフパイは、細やかな層が生み出す豊かな食感で、特別なシーンでの餞別に適しています。
まとめ
餞別は感謝と激励の気持ちを込めて贈られる日本独自の文化であり、お返しの有無や方法はシーンや相手との関係性によって変わります。一般的に退職時はお返し不要とされますが、異動や栄転の際にはお返しを用意するのが望ましいケースも多くあります。大切なのは形式にとらわれすぎず、心を込めた感謝を相手に伝えることです。
お返しの品に悩んだときは、個包装のお菓子や実用的なギフトが安心です。門前仲町の老舗「みなとや」では、ありがとう煎餅やプチギフトなど、餞別にふさわしい商品を多数取り揃えています。感謝をかたちにする贈り物を探している方は、ぜひみなとや公式サイトをご覧ください。